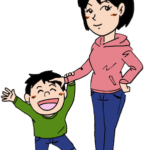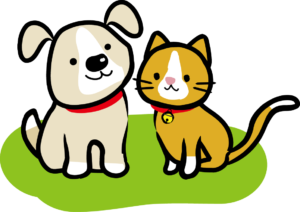民法改正:養育費の支払い確保
1、先取特権(改正後民法第306条3号)
今回の民法改正により、養育費債権に先取特権を付与。債務名義がなくても、養育費の支払いに関し、取り決めがあれば担保権実行という形式で強制執行ができるようになりました。
離婚後、子供を養育する母親など、養育費請求権を有する債権者は、調停調書や判決書などの「債務名義」がなくても、「その存在を証する文書」(離婚協議書など)(民事執行法第181条1項4号)を提出することにより、債務者(元夫など)の財産の差押えの申立てが可能となりました。
これまでは、養育費が支払われない場合、裁判所に調停申立や訴訟を提起する必要がありましたが、今後このような手続が不要になるケースがあります。
差し押さえることのできる割合ですが、養育費支払い義務者の給与を差し押さえる場合、その1/2まで差し押さえることができます。
2、法定養育費の創設(改正後民法第766条の3)
父母が離婚の際に養育費の取り決めをした場合、先取特権によって従来よりも支払の確保ができるようになりました。
しかし、養育費を定めることは協議離婚の条件ではないことから、養育費を決めないまま協議離婚をしてしまう場合があります。
また、DVや虐待があったため、離婚時に養育費の話合いができないまま離婚しなければならない場合もあるでしょう。
そこで、今回の民法改正により、父母の協議による定めがない場合の補充的なものとして、法定養育費制度が設けられました(改正後民法第766条の3)。
請求権者は、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う者です。
法定養育費の額にですが「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされています。
3、収入についての情報開示
養育費に関する取り決めをするにも、養育費の額は当事者双方の収入を基礎に算出するので、義務者の収入が明らかでなければ適正な養育費の額を算出できません。
そこで、養育費請求の申立て(人事訴訟法第32条1項)がされている場合、必要があると認められるときは、家庭裁判所は当事者に対し、その収入及び試算の状況に関する情報を開示することを命ずることができる旨の制度が新設されました(改正後人事訴訟法第34条の3、改正後家事事件手続法第152条の2第1項)。
4、財産開示手続き
今回の民法改正により、養育費債権に関し、債務名義がなくとも先取特権によって、情報取得手続ができるものとしました(改正後民事執行法第206条2項)。
たとえば、養育費が未払いとなっており、養育費支払い義務者(元夫など)の給与を差し押さえたいが、現在の勤務先がわからない場合、給料の支給者に関する情報を、第三者である市区町村、日本年金機構などから提供してもらうことができます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市 マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」
マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月1日死後事務委任契約。亡くなったことを知らせるには
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月1日死後事務委任契約。亡くなったことを知らせるには