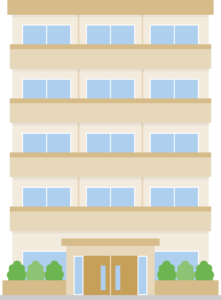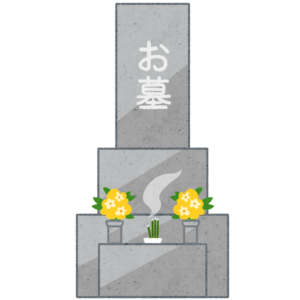相続
生命保険の受取人を孫にすると
生命保険金の相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数。
孫は法定相続人に該当しないため、孫が生命保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠は適用されません。相続税がそのままかかります。
管理会社の側から管理委託契約を解除するには
甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる(マンション標準管理契約書第19条)。
生命保険契約照会制度
「生命保険契約照会制度」とは、全国の生命保険会社(42社)が加入している「一般社団法人生命保険協会」に、亡くなったご家族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を調べてもらうことができる制度です。
死亡時の健康保険の手続き
健康保険は、サラリーマンなどの民間企業等に勤めている人やその扶養されていた家族が加入する医療保険制度です。
個人ごとに年齢や収入に応じて保険料が算定され、その半分を個人が負担、もう半分を勤務先の企業が負担します。
「団信」と一般の死亡保険の違い
「団体信用生命保険(団信)」は、住宅ローンを契約するときに同時に加入する生命保険です。
多くの場合、ローン契約の条件として団信への加入が必須となっています。
住宅ローンが残っている場合の相続
「団体信用生命保険(団信)」は、住宅ローンを契約するときに同時に加入する生命保険です。
多くの場合、ローン契約の条件として団信への加入が必須となっています。
住所で不動産を特定してしまった遺言書の有効性
住所で不動産を特定=遺言全体が無効、ではないです。
ただ、一見住所さえ書いていれば不動産は特定できそうだと思うでしょう?。
しかし、実際はそうではありません。
「地番」とは?。住所との違い
「地番」とは、法務局が定めた住所です。
「住居表示」とは、住居表示法に基づいて市町村が定めた住所です。
地番と住居表示番号は定めた機関が違う、全く別の番号です。
故人が利用していた証券会社が分からない場合
故人が利用していた証券会社がそもそも分からない場合、①証券会社に関する書類を探す②ネット証券なら、故人のスマホやパソコンも確認、の方法もありますが、それでも分からなければ、証券保管振替機構(ほふり)にて情報開示請求を行いましょう。
故人に借金があったかどうか調べる方法
故人に借金があったかどうか調べる方法としては、
①故人の信用情報を、信用情報機関に開示請求をする
②故人へ届く郵便物を確認する
が挙げられます。
権利証がない時の「本人確認情報」の提供
権利証の提出が必要になるのは、抽象的に書くと、登記申請者が、該当の不動産に対し、「自身が権利を持っていること」を証明した上で申請することが必要な登記申請の場合です。
外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?
相続税の納税義務者については、原則として、
亡くなった方が
①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合
および
②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合
遺留分の基礎となる財産
「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法第1043条)
公正証書遺言でも遺留分を請求できる
「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
この権利は遺言によっても奪うことはできません。
配偶者居住権の相続税評価額
夫の遺産:自宅5000万円、預金1000万円
相続人:妻、長男
配偶者居住権の評価額:2500万円
法定相続分通り分けると、妻と長男各3000万円。
妻が実家を相続したとして、長男に不足分2000万円を支払う、は現実の問題難しいでしょう。
配偶者居住権の落とし穴
「配偶者居住権」とは、亡くなった方が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。
従来、配偶者が相続によって実家の所有権を獲得しても、他の相続人とのバランス上、預貯金等の相続を諦めざるを得ませんでした。しかし、これでは、住む家は確保できても、生活するのに困ることになります。
「配偶者居住権」は「無償での住居の確保」と「バランスの良い遺産分割」の双方のバランスを考慮した制度といえます。
特別寄与料の計算方法
「特別寄与料」とは、相続人でない人が亡くなった被相続人に対して特別に貢献した場合に、その貢献に見合ったものとして支払われる金銭のことをいいます。
2018年民法改正により、特別寄与料制度が創設。被相続人に対して介護や看護などで貢献した親族は、相続人でなくても財産を得られるようになりました。
自動車保険の等級を引継くことはできるか?
自動車保険の等級は通常6等級からはじまり、1年間事故がなければ翌年の更新時には1等級上がります。
等級が上がれば割引率も大きくなります。
この等級は、記名被保険者を同居の家族に変更する時に引継ぐことができます
配偶者であれば別居でも可能です。
もしもに備えた空き家管理サービス
少子高齢化による人口減少で、空き家の増加が社会問題化されています。
かつ、遠隔地に住んでいる等、管理されていない空き家が増加。
2014年に施行された「空き家対策特別措置法」により管理されていない空き家に対し、公的な介入や罰則が適用可能となりました。
韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。
樺太、北方領土、満州の戸籍は?
旧樺太の戸籍ですが、ほとんどが戦乱により滅失してます。
一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができます。
FXポジションを相続する手続き
「FXポジション」とは、損益が確定していない買い注文や売り注文のことです。
安く買って、高く売るか、または高い時に売って、安い時に買えば利益が出るわけですが、買ってからまだ売っていない状態、売りに出してからまだ買っていない状態が「ポジション」という状態です。
故人の「仮想通貨」。相続できる?
「仮想通貨」とは、暗号資産と呼ばれている金融資産です。
ビットコインはその代表例。
国内においては資金決済法で通貨に近い性質を持つものと提示されており、資産として相続税の対象になります。
相続発生後サブスク契約を解約するには
「サブスク」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約しない限り自動的に支払いが継続されます。
「空き家は放置せず「仕舞う」(除却)「活かす」(活用)で住み良い街に
所謂「団塊の世代」が全員75歳になり(2025年問題)、相続が急激に増え、空き家が急激に増加する。
2013年の総務省調査によると全国の空き家数は約820万戸、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっていました。
これが、民間予測によると、2033年頃には空き家数2150万戸、なんと全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまいます。
被相続人(亡くなった方)が外国人の場合
外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、
(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。
被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
農地を家族信託するには
農地を農地の状態のまま、家族信託する場合には農地法3条の許可が必要となりますが、信託の受託者となることができるのは、農業協同組合など一定の法人に限定されており、個人が受託者になるのは難しいです。