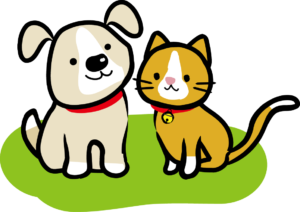2025年4月6日
「市民葬・区民葬」とは、各市町村が市民・区民向けのサービスの一環として行っている葬儀プランです。
2025年4月4日
「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。
2025年4月1日
「換価分割」とは、不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法をいいます。
2025年4月1日
「換価分割」とは、不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法をいいます。
2025年3月31日
◎事例
父親既に死亡。
母親から「不動産を長男に相続させる」旨の遺言を書いたところ、母親が認知症になったのを受けて、家庭裁判所への申し立てにより弁護士Aが後見人に選任されました。
2025年3月31日
(1)不動産を売却、贈与などで処分した場合
遺言書に不動産の行き先について記載しても、処分は可能です。
2025年3月30日
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
2025年3月30日
預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。
2025年3月29日
遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
2025年3月29日
残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。
ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。
2025年3月29日
「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
2025年3月29日
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
2025年3月27日
被相続人(亡くなった方)の投資信託は当然には分割されず、遺産分割の対象になります(最高裁平成26年12月25日)。
2025年3月26日
「失踪宣告」とは、生死が分からない行方不明の人に対し、要件を満たすと法律上死亡したとみなす制度のことです。
2025年3月26日
「失踪宣告」とは、生死が分からない行方不明の人に対し、要件を満たすと法律上死亡したとみなす制度のことです。
2025年3月21日
契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。
2025年3月21日
(1)遺言書
相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。
2025年3月19日
「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。
2025年3月19日
「数次相続」とは、相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。
2025年3月19日
未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。
相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。
2025年3月18日
祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。
2025年3月18日
二世帯住宅が親との共有名義の場合、親の共有持分が相続の対象となります。
2025年3月17日
「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます
(民法第904条の2)。
2025年3月17日
端株(単元未満株)は証券会社の口座ではなく、株主名簿を管理する信託銀行の「特別口座」で管理されてます。
2025年3月16日
自動車の名義変更ですが、必要書類を揃えて運輸支局に手続きをしに行きます。
2025年3月13日
被相続人(亡くなった方)が借金などの債務を残して死亡した場合、原則「法定相続人全員の債務」となります。
2025年3月13日
「財産目録」とは、被相続人の財産の内容がわかるよう、不動産、預貯金など、種別ごとに一覧にしたものです。
2025年3月8日
◎事例:
旦那さん死亡。
相続人:配偶者、長男。しかし、長男は父親と仲が悪く長年、絶縁状態。
相続財産:自宅、預貯金
2025年3月5日
「管理不全土地(建物)管理制度」とは、所有者もその所在も判明しているものの、適切な管理がされていない土地、建物について、利害関係人が裁判所に申立てを行い。裁判所が管理する必要を認めた場合、土地、建物の管理を行う管理人を選任。管理命令が発令される制度です。
2025年3月5日
これまでも、財産管理制度には、
㋐所有者の所在が不明な土地、建物の管理や処分が必要な場合
「不在者財産管理制度」(民法第25条)
2025年2月26日
父親死亡。
相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の障害者)。
2025年2月26日
◎事例
㋐両親既に死亡
㋑長男は子なし夫婦
㋒次男は重度の障害者。成年後見人が付いている
2025年2月24日
部屋の中で人知れず死亡。発見が遅れると、血液や体液などによる汚れが床や壁に付着していたり、害虫が発生していたりと、部屋を通常の清掃で綺麗にするのが難しくなります。
2025年2月21日
亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
2025年2月18日
「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人(親、子供、配偶者)に最低限保障される遺産取得分です。
2025年2月17日
遺言執行者となることのできる資格ですが、未成年者や破産者以外は遺言執行者となることができます(民法第1009条)。
2025年2月16日
遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。
2025年2月12日
(1)サブスクなど有料なサイトの解約
携帯電話やスマホ経由で契約していて契約が自動更新される場合、料金の支払いを止めるためには契約を解除するしかありません。
2025年2月11日
「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐことです。
2025年2月9日
令和6年11月11日に父親が死亡。そして、母親が翌年2月2日に亡くなった。
2025年2月9日
Q:父親死亡。相続人は母親、長男、次男でしたが、父親に借金があったので次男は相続放棄。
2025年2月9日
Q:父死亡。子供全員が相続放棄しました。これで母に全財産わたる?
2025年2月8日
「直葬」とは、通夜式や告別式などの儀式を省き、火葬のみを行う葬儀のことをいいます。
2025年2月8日
「0葬(ゼロソウ)」とは、火葬を行った後に火葬場から「遺骨」を引き取らないことをいいます。
2025年2月5日
(1)法務局での相続登記
まずは、法務局で不動産の名義人を変更する手続き(所有権移転登記)が必要です。
2025年2月5日
(1)山林を貸し出して活用することができる
自治体や林業を行っている業者などに貸し出すことにより、利益を得られる可能性があります。