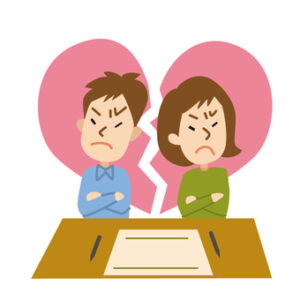普通預貯金債権などは遺産分割の対象です
1、最高裁平成28年年12月19日判決
㋐共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく
㋑遺産分割の対象となる
2、従来の判例と銀行実務
これまでの判例は「相続人が複数いる場合には、預貯金については相続に伴い法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」でした。
つまり、原則として預貯金は、相続により各相続人に当然に分割承継されるので遺産分割の対象とならない、でした。
したがって、例えば、被相続人(亡くなった方)の銀行口座に1000万円の預金があり、相続人が2人だったとすると、相続人各々が銀行に対し500万円ずつ支払うように求めることができる、でした。
もっとも、銀行実務では、当時から金融機関が口座保有者の死亡を確認した場合、被相続人名義の預貯金を凍結し、その払い戻しを制限していました。
たとえ従来の最高裁判決にしたがい、遺産分割をしないまま。各相続人が自己の法定相続分に応じた預貯金の払い戻しを求めても、多くの場合金融機関は払い戻しに応じていませんでした。
3、まとめ
上の平成28年最高裁判決の決定は、金融機関に実務上の取り扱いに法律的な解釈が近づいたと考えることが出来ます。
ある相続人に相続分の預貯金を払い戻した後、その預貯金を含む遺産分割協議が成立すれば、その遺産分割協議に応じてもう一度払い戻しをやり直さないといけないとすると、金融機関が相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまうリスクが発生してしまいます。
なので、金融機関が被相続人の死亡を知ると口座を凍結するのにも一応の理由があるといえます。
金融機関が被相続人の口座を凍結してしまう対応策としては以下のものを挙げることができます。
①葬儀費用などのすぐに必要になりそうな資金は、口座が凍結する前に引き出しておく。
②生命保険に加入。相続開始後すぐに相続人が保険金を受け取れるようにし、まとまったお金を確保できるようにしておく。
③生前に遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成。遺言執行者を指定しておくことにより、速やかに凍結解除。必要な費用の引き出しできるようにしておく
生前のうちに準備しておきましょう。
~関連記事~
貯金口座は「凍結」。遺族が預貯金を引き出すことができなくなります。
凍結した預貯金を引き出せるようにするためには、銀行口座の相続手続を行う必要があります。
山梨県、甲府市で
①相続人の確定のための戸籍取得
②銀行との打ち合わせ。相続手続き書類の作成
③残高証明書の取得による預貯金の調査
④遺産分割前の預貯金の仮払い制度の利用
⑤遺産分割協議書の作成
⑥預貯金の解約手続き
など、銀行口座の相続手続きでお困りでしたら行政書士に相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約
ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市