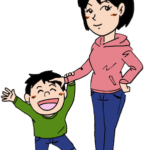遺産分割による代償譲渡
1、遺産分割による代償譲渡
「遺産分割による代償譲渡」とは、「代償分割」の方法により、贈与税の負担なく、親(被相続人)から子供(相続人)へ不動産を移すことをいいます。
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法をいいます。
「遺産分割代償譲渡」の場合、他の相続人に渡すのは代償金ではなく不動産です。
2、「遺産分割による代償譲渡」の手続き
(1)相続人全員により遺産分割協議を行う
↓
(2)不動産を持っている相続人が、最低でも当該不動産の価額に相当するだけの遺産を取得する。
↓
(3)その遺産を取得する代償として、不動産を持っている相続人は、自分が所有する不動産を、他の相続人に贈与する。
↓
(4)(2)(3)の内容の遺産分割協議書を作成。相続人全員で署名、押印(おういん)する。
↓
(5)この不動産譲渡に伴い譲渡益(譲渡所得)が発生する場合、譲渡の翌年に確定申告を行い、納税する。
3、具体的事例
㋐父親死亡。相続人は母親(妻)と子供
㋑父親の相続財産は実家(不動産:相続税評価額3000万円)と預貯金(2500万円)。
㋒母親は賃貸マンション(相続税評価額2000万円)を所有。二次相続対策として子供への譲渡を考えている
以下の内容の遺産分割協議を行った
①子供が実家を、母親が預貯金を取得する
②母親は預貯金を取得する代償として所有する賃貸マンションを子供に贈与する
譲渡する賃貸マンションの相続税評価額より、取得する預貯金の方が高いので贈与税は課されません。
逆に低いと差額につき贈与税が課されてしまいます。
4、「遺産分割による代償譲渡」後の相続税節税効果
上の事例において、「遺産分割による代償譲渡」実行後、母親は代償譲渡した不動産の分財産が減少しますが、一方で取得した遺産(預貯金)の分、差し引きすると財産が増えることになります。
その後母親が取得した遺産(預貯金)を子供に少しずつ贈与(年間110万円までは贈与税非課税)することにより、財産を減らし、将来の相続税節税を図ることが可能となります。
また、取得した遺産で子供を受取人とする生命保険に入ることにより、将来の相続の際、死亡保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する方法もあります。
5、「遺産分割による代償譲渡」による認知症対策
上の事例で、将来母親が認知症になり、介護施設の入所費用等でお金が必要になった際には不動産を売却しようと考えていた場合
母親が子供に贈与しようとすれば、高い贈与税がかかります。
母親のために、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする、もありますが、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあるので、安易な利用は避けたい所です。
そこで、父親の死亡時に「遺産分割による代償譲渡」により、母親所有の賃貸マンションを子供に贈与しておけば、子供が賃貸マンションを売却することにより、介護施設の入所費用等に充てることができます。
ただ、ディメリットは「父親の死亡時」じゃないと利用できないこと。
父親の死亡前に母親が認知症になったらこの方法は使えません。
6、「遺産分割による代償譲渡」による共有不動産の共有状態解消
◎事例:
父親死亡。父親所有の実家(不動産)を法定相続分通り、母親(1/2)、長男(1/4)、次男(1/4)に分けた場合
母親死亡。相続財産は実家と預貯金
遺産分割協議により
①長男が母親の遺産である共有持分1/2を相続する。
②次男が母親の遺産である預貯金を相続する。
③次男は預貯金を相続する代償として、自分の所有する共有持分1/4を長男に対して贈与する。
前提として、次男の取得する預貯金≧共有持分1/4の価額
7、「遺産分割による代償譲渡」を利用する注意点
(1)贈与税が発生することも
「遺産分割協議書」に「財産を取得する代償として所有する不動産を贈与する」という趣旨の記載をすれば原則贈与税を課されることはありません。
記載がないと、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。
また、相続した財産より不動産の相続税評価額の方が高い場合、贈与と認定され、贈与税が課税されることもあります。
(2)譲渡所得税が課されることも
贈与した不動産の時価が取得費よりも高い場合、譲渡所得が発生します。
譲渡所得の金額=時価ー取得費
所得税の額=譲渡所得×税率(20.315%)
※参考:「国税庁HP「取得費となるもの」
(3)配偶者控除、小規模宅地等の特例が使えなくなることも
上の事例で「遺産分割による代償譲渡」を使わなくても、一次相続で母親が「配偶者控除」もしくは「小規模宅地等の特例」を使った方が、また二次相続で子供が「小規模宅地等の特例」を使った方が、結果的に一次相続、二次相続を通じて相続税の節税になることもあります。
逆に書くと、これらの特例が使えない結果、場合によっては相続税が高くなることがあります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市 マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」
マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」