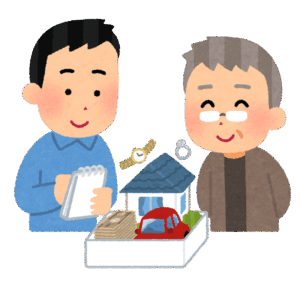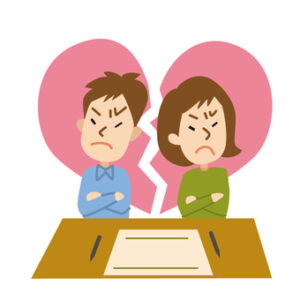死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に:2025年10月1日より
1、死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に 「死後事務委任契約公正証書」の目的の価額による手数料は、手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額です(日本公証人連合会HPより)。 公証人に対する手 […]
任意後見契約公正証書の手数料。2025年10月1日より13000円に
1、任意後見契約公正証書の手数料 任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき13000円(従来は11000円)。 それに証書を紙に出力した場合の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により3枚を超えるときは、超える1枚ご […]
公正証書の作成手続がデジタル化されます!:2025年10月1日より
1、2025年10月1日より公正証書の作成手続がデジタル化 主な柱は3つ。 (1)インターネットによる嘱託が可能に! ㋐従来:公証役場に来所して、印鑑証明書等の書面により本人確認 ㋑新たに追加:電子データ(嘱託に係る情報 […]
貸金庫に遺言書を保管したかも…。どうする?
1、貸金庫に入れてはいけないもの 「貸金庫に入れてはいけないもの」の一つに遺言書があります。 相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。 相続人が貸 […]
複数本ある印鑑で「銀行印」が分からなくなったら
1、銀行印 「銀行印」とは、預金口座を開設する際に登録した印鑑のことをいいます。 口座名義人を証明するために必要です。 2、預金の払戻請求 銀行の窓口にて預金の払い戻しを申請する際には「払い戻し請求書」に ①氏名 ②口座 […]
孫への生前贈与。「特別受益」に該当する?
1、特別受益 「特別受益」とは、亡くなった方からの遺贈または贈与によって、相続人が得た特別の利益をいいます(民法903条1項)。 具体的には、以下の遺贈・贈与が特別受益に該当します。 以下のいずれかに該当する贈与㋐婚姻の […]
「事業承継税制」の取消事由
1、事業承継税制 「事業承継税制」とは、中小企業の事業承継において、条件を満たせば事業承継に関する贈与税や相続税の納税を猶予・免除される制度のことをいいます。 中小企業庁が中小企業を支援するために、「中小企業における経営 […]
事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る:Yahoo NEWS
1、事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る Yahoo NEWSは「こちら」。 記事にもある通り、たとえ、延長決定。引き続き贈与税、相続税が免除となっても、中小企業の7割が赤字の現状が示す通り、以前苦しい。 しか […]
認知症サポート信託:みずほ信託銀行
1、認知症サポート信託 ◎手続き (1)ご本人様。みずほ信託銀行に金銭を預け入れる。信託金額は500万円以上。 ↓ (2)ご本人様。認知症の発症に備え、預けたお金の手続きを代理で行う「手続代理人」を、原則としてご本人さま […]
法定相続人の中に認知症の方がいる場合
1、認知症の相続人がいる遺産分割協議は無効 遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。 しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産 […]
親が認知症になったら
1、銀行口座、貸金庫の確認 親が認知症を発症すると、介護費用、医療費用など、様々な費用が発生することが予想されます。 まずは、親の銀行口座(普通預金と定期預金)の確認をしておきましょう。 銀行口座を確認するには、親の通帳 […]
「たくす株」:マネックス証券
1、たくす株 「たくす株」は、株式投資をしている方に向けた、認知症を発症した際の財産管理と、相続時のスムーズな資産承継をサポートするサービスです。 認知症を発症すると、様々な取引ができなくなる「資産凍結」のリスクがありま […]
[事例]70代男性。配偶者、子供はいない。遺産は?。葬儀は誰が行う?
1、事例 ㋐70代男性。配偶者、子供、兄弟はいない。父母は既に死亡。 ㋑遺産はどうなる?。できれば生前に準備しておきたい。 ㋒葬儀は?。同じく生前に準備しておきたい。 2、相続人の不存在 本問の場合、70代の男性には配偶 […]
[事例]叔父死亡。借金の督促状が来た場合、姪は相続放棄できる
1、事例 ㋐叔父死亡。プラスの財産はほとんどなし。1000万円の借金がある ㋑叔父には配偶者、子供はいない。両親は既に死亡 ㋒相談者(叔父からすれば姪)の父親(叔父からすれば弟)は既に死亡。他に叔父の兄弟はいない。 2、 […]
[事例]アメリカ人と結婚。出生による子供の米国籍の取得
1、事例 ㋐アメリカ人の男性と国際結婚。永住権を取得。 ㋑現在妊娠中。夫の仕事の関係上しばらく日本に滞在。日本で出産しようと考えている。 ㋒子供には将来的に日本か米国籍を選ばせてあげたい。日本で生まれた子供米国籍を取らせ […]
[事例]母親。父親の死後「姻族関係終了届」提出。娘に父親の母(祖母)の介護義務は?
1、事例 ◎事例 ㋐夫死亡。生前から妻と夫の父母は仲が悪かったため、妻。市区町村役場に「姻族関係終了届」提出 ㋑夫の父親死亡後、夫の母親。自宅で転倒。大腿骨を骨折して入院・手術。通院が必要となった。 ㋒そこで、夫の母親。 […]
「姻族関係終了届」を提出しないで再婚すると
1、姻族関係終了届(死後離婚) 「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。 結婚すると、一方の配偶者と他方の配偶者の […]
相続放棄しても受け取れるもの
1、相続放棄しても受け取れるもの 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)。 しかし、法律上で相続財産に含まれないものについては取得することができます。 (1)生命保険金(死 […]
在留資格「留学」→「家族滞在」
1、在留資格「家族滞在」 在留資格「家族滞在」とは、「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」などで働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。 ◎要件 ①結婚していること ②同居していること […]
在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)
1、在留資格「経営・管理」 在留資格「経営・管理」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。 (1)経営者 日本国内に事業所を有する […]
二重国籍を認めない国籍法 国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁
1、国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁 Yahoo NEWSは「こちら」。 婚姻によるカナダ国籍の付与はありません。 自己の志望により外国の国籍を取得したときには、日本国籍を失 […]
単身高齢者、借りやすく 大家の不安軽減へ改正住宅セーフティーネット法10月1日施行:Yahoo NEWS
1、改正住宅セーフティーネット法10月1日施行 Yahoo NEWSは「こちら」。 単身高齢者が借りやすくなると同時に大家さんのリスクが減るようにしないと中々登録は増えないのでは。 ①見守り契約。「孤独死保険」の加入義務 […]
在日韓国人死亡。相続放棄するには
1、韓国人が死亡した際の相続手続き (1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。 ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている […]
在日韓国人死亡。韓国の銀行の相続手続き
1、韓国人が死亡した際の相続手続き (1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。 ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている […]
韓国民法。配偶者の相続分
1、韓国人が死亡した際の相続手続き (1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。 ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている […]
インド人との国際結婚手続き(先にインドで手続き)
1、先にインドで手続き (1)在インド日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得 ◎日本人が用意する書類 ①申請書 ②戸籍謄本 ③本人確認書類:運転免許証、パスポートなど ④パートナーのパスポートのコピー(身分事項のページ […]
インド人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き (1)インドの役所で各書類を用意 ①宣誓供述書:本人の独身を証明するもの ②親族の申述書:親族が本人の独身を証明。インドの裁判行政官が認証したもの ③未婚証明書:所属州大臣が発行したもの ↓ (2) […]
「パスワードが分からない」どころの騒ぎじゃない。パスキー時代に想定されるデジタル遺品問題とは:Yahoo NEWS
1、パスキー時代に想定されるデジタル遺品問題とは Yahoo NEWSは「こちら」。 (1)故人が株式を預けている証券会社が分からない場合、「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもら […]
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の外国人。解雇されたら
1、出入国在留管理庁に届出 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は 「特定の会社に雇用され、その会社で専門的な業務に従事すること」が前提 なので、雇用契約が終了した時点で在留資格の内容と実際の活動内容が合わないことにな […]
ホテルのフロント。「国際業務」ではなく「人文知識」で申請も…
1、在留資格「国際業務」の要件 ◎学歴 ①大学を卒業: 日本、海外を問いません ②専門学校を卒業: 日本の専門学校、かつ、従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが必要です。 ◎実務経験 大学を卒業している場合 […]
外国人がホテルフロント業務を行うには
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」 「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業 […]
「DV等支援措置」。戸籍謄本は対象外
1、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置 DV等を受けた配偶者、元配偶者に新住所を知られたくない対策として「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」という国の支援制度があります。 申し出ることにより、支援措置が必要かど […]
[事例]自分の子供(既に死亡)が外国人と結婚している場合、親は遺言書を残すべき
1、事例 ㋐長男(既に死亡)が中国人と結婚していた。 ㋑長男の奥さんとその子供(父親から見て孫:中国国籍)は長男の死亡を機に中国に帰国している ㋒父親が亡くなれば、相続人は母親、長女と長男の代襲相続により長男の子供(父親 […]
【最新お墓事情】少子高齢化で墓の維持管理が大変「継ぐ人がいない」…“墓じまい”を選ぶ人も :Yahoo NEWS
1、【最新お墓事情】少子高齢化で墓の維持管理が大変「継ぐ人がいない」…“墓じまい”を選ぶ人も Yahoo NEWSは「こちら」。 「墓じまい」後、一番費用がかからない方法として散骨もしくは合祀墓、があります。 両者の共 […]
兄弟姉妹の戸籍謄本を取得するには
1、原則として本人のみ取得できる 戸籍謄本の取得は、原則として本人または同一戸籍の親族に限られます。戸籍謄本の取得ができる同一戸籍の親族とは、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)です。 傍系親族(兄弟姉妹、いとこ、叔父 […]
億の遺産を独り占め…守銭奴のごとき50代独身兄に「余命宣告」。死後に発覚した〈あんまりな仕打ち〉:Yahoo NEWS
1、億の遺産を独り占め…守銭奴のごとき50代独身兄に「余命宣告」。死後に発覚した〈あんまりな仕打ち〉 Yahoo NEWSは「こちら」。 知らない間に独身の兄が「できちゃった婚」をしてすぐ離婚。子供が1人いる。 「できち […]
【義父母との同居介護が招く相続トラブル】義兄が「遺産目当てか」と疑心暗鬼に:Yahoo NEWS
1、【義父母との同居介護が招く相続トラブル】義兄が「遺産目当てか」と疑心暗鬼に Yahoo NEWSは「こちら」。 義父が遺言書を残していないと遺産分割協議となりますが、あくまでも相続人は義母(妻の母)と妻と妻の兄(義兄 […]
障害のある子供を持つ親亡き後の対策(生命保険信託)で上手くいかないケース
1、生命保険信託 「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金によ […]
相続人に知的障害の方がいる場合、生前の内に公正証書遺言の作成を
1、遺言書を作成しておかないと ◎事例: 父親死亡。 相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の知的障害者)。 父親が遺言書を残していないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男は重度の知的障害者な […]
死後の手続きは想像以上に大変!「子どもがいたら安心」は大間違い。
1、死後の手続きは想像以上に大変!「子どもがいたら安心」は大間違い。 Yahoo NEWSは「こちら」。 少子化、高齢化が進み、家族、親族の関係が薄くなっている今、いわゆる「おひとり様」でなくても生前、死後含め準備してお […]
生活困窮者自立支援制度
1、生活困窮者自立支援制度 「生活困窮者自立支援制度」は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度のことをいいます。 生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの […]
実家に残る未婚、無職の妹(56)をどうすればいいのか:Yahoo NEWS
1、実家に残る未婚、無職の妹(56)をどうすればいいのか Yahoo NEWSは「こちら」。 確かに「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第877条1項)とあり「扶養義務」があります。 しかし、それ […]
被相続人が台湾人。戸籍を揃えることができない場合
1、台湾人が死亡した際の相続手続き 台湾籍の方が日本で亡くなった場合、相続には台湾の法律が適用されます。 台湾籍の方が日本法における遺言書を残した場合、日本法(民法)に適合していれば有効です。 2、法定相続人 順位 台湾 […]