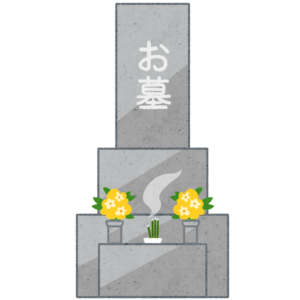相続手続き
故人のネット銀行、ネット証券を探すには?
1、ネット銀行 ネット銀行とは、従来の銀行のような対面店舗を持たず、インターネット上での取引を中心として営業する銀行のことをいいます。 ネット銀行の場合、銀行員と対面で相続手続きの相談をすることができないのが店舗型の銀行 […]
戸籍証明書等の広域交付:戸籍の附票などは対象外
1、戸籍証明書等の広域交付 これまでは、各本籍地から戸籍謄本を取得する必要があったので、本籍地が何度も変わると、過去の本籍地一つ一つに戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。 特に、直接窓口に出向くことができない遠方の […]
山梨中央銀行の相続手続き
1、相続手続きの流れ (1)手続きの申出 事前に来店もしくは電話にて連絡 ◎必要書類 ①被相続人の取引内容のわかるもの:通帳・キャッシュカードなど ②亡くなったことがわかる戸籍謄本など ③相続人であることがわかるもの:戸 […]
甲府信用金庫の相続手続き
1、相続手続きの流れ (1)手続きの申出 事前に来店もしくは相続手続き専用フリーダイヤルに連絡 ◎必要書類 ①被相続人の取引内容のわかるもの:通帳・キャッシュカードなど ②亡くなったことがわかる戸籍謄本など ③相続人であ […]
山梨信用金庫の相続手続き
1、相続手続きの流れ (1)手続きの申出 事前に来店もしくは電話で連絡 ◎必要書類 ①被相続人の取引内容が分かるもの:通帳・キャッシュカードなど ②来店者の本人確認書類:運転免許証など ↓ (2)必要書類の準備 ↓ (3 […]
兄弟姉妹が相続人。必要な戸籍は?
1、兄弟姉妹が相続人になるケース (1)相続人が配偶者と兄弟の場合 配偶者の法定相続分は相続財産の3/4、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の1/4です。 (2)相続人が兄弟のみ 亡くなった方に配偶者、子供、孫、親、祖父母が […]
ゆうちょ銀行の相続手続き:少額なら簡易手続き
1、簡易手続き ゆうちょ銀行に少額の貯金(100万円以下)しかない場合、通常とは別の簡易な手続きを行うことができます。 簡易な手続きを利用すると、貯金等相続手続請求書のすべての項目に、相続代表人が1人で記入して手続きが終 […]
ゆうちょ銀行の相続手続き:被相続人名義で開設している口座の有無の調査
1、現存調査(貯金の有無の調査) 相続発生後、ゆうちょ銀行の相続手続きを進めるには、相続発生の連絡。「相続確認表」を記入、提出することになりますが、被相続人(亡くなった方)がゆうちょ銀行の口座、通帳をいくつ持っているか分 […]
貸金庫に遺言書を保管したかも…。どうする?
1、貸金庫に入れてはいけないもの 「貸金庫に入れてはいけないもの」の一つに遺言書があります。 相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。 相続人が貸 […]
「姻族関係終了届」を提出しないで再婚すると
1、姻族関係終了届(死後離婚) 「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。 結婚すると、一方の配偶者と他方の配偶者の […]
兄弟姉妹の戸籍謄本を取得するには
1、原則として本人のみ取得できる 戸籍謄本の取得は、原則として本人または同一戸籍の親族に限られます。戸籍謄本の取得ができる同一戸籍の親族とは、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)です。 傍系親族(兄弟姉妹、いとこ、叔父 […]
個人事業主が亡くなった場合の相続手続き
1、個人事業主が亡くなったら (1)死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出 (2)廃業届 死亡した日から1カ月以内に、開業届を出している税務署に提出。 (3)事業廃止届 被相続人が課税事業者だった […]
死亡届の手続きを葬儀会社に任せられる理由
1、死亡届 「死亡届」は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。 =届出義務者= 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87 […]
高齢者が役所に行かないで印鑑登録するには
1、印鑑証明書 「印鑑証明書」とは、自治体に登録した印鑑が、登録した本人の印鑑に間違いないことを証明するための書類のことをいいます。 印鑑登録された印鑑(実印)でハンコを押し、印鑑登録書を提出することにより、登録した本人 […]
死亡届記載事項証明書
1、死亡届記載事項証明書 死亡届は ㋐左半分:届出人が記入する事項(死亡者や届出人に関するもの) ㋑右半分:病院等が記入する死亡診断書(死体検案書) となっています。 死亡届の原本は、死亡を届出る際に市区町村役場に提出後 […]
普通預貯金債権などは遺産分割の対象です
1、最高裁平成28年年12月19日判決 ㋐共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく ㋑遺産分割の対象となる 2、従来の判例と銀行実務 […]
相続手続きで「印鑑証明書」が必要なもの
1、印鑑証明書 「印鑑証明書」とは、自治体に登録した印鑑が、登録した本人の印鑑に間違いないことを証明するための書類のことをいいます。 印鑑登録された印鑑(実印)でハンコを押し、印鑑登録書を提出することにより、登録した本人 […]
生前に相続放棄はできません
1、生前に相続放棄はできません 「相続放棄」とは、被相続人の相続権を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続のことをいいます。 一般的には、相続人が被相続人(亡くなった方)のマイナスの財産(借金など)を相続しないために利用さ […]
遺産から葬儀代を出しても相続放棄できる
1、単純承認が成立 「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続人は「単純承認」したものとみなされます(民法第921条1項)。 ◎具体例 ①相続財産の使い込みや譲渡 ②預貯金の払い戻しや解約 ③遺産分割協議に参 […]
相続手続きをしなかったら
1、相続手続きをしなかったら 相続手続きをしないままで放置したとしても、原則罰則はありません。 ただし、例外があります。 (1)相続登記 2024年(令和6年)4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、 […]
JAバンクの相続手続き
1、JAバンクの相続手続き (1)JAバンクに口座の名義人が死亡した旨伝える 通帳もしくはキャッシュカードを準備し、口座がある支店に連絡します。 ↓ (2)「残高証明書」の請求 ◎必要書類 ①相続貯金等残高証明依頼書 ② […]
名義人の死亡後、公共料金(電気、ガス、水道など)を解約するには
1、公共料金の解約(電気、ガス) 電気、ガスの場合、契約している電力会社、ガス会社に連絡をします。 現在は電気、ガスが自由化されています。 亡くなった方が契約していた電力会社やガス会社。契約番号などを確認するには、 ①電 […]
相続人の中に行方不明者がいる場合、貸金庫の中身を確認するには:事実実験公正証書
1、契約者死亡後に貸金庫の中身を確認する方法 契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。 遺産分割協議書又は金融機関所定の同意を証する書面に、相続人全員が実印を押印(おういん […]
ネット銀行の相続。銀行名さえ分かれば相続手続き出来ます
1、ネット銀行 ネット銀行とは、従来の銀行のような対面店舗を持たず、インターネット上での取引を中心として営業する銀行のことです。 ネット銀行の場合、銀行員と対面で相続手続きの相談をすることができないのが店舗型の銀行との大 […]
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を簡単に集められるように:「戸籍証明書等の広域交付」
仮に、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合、せっかく成立した遺産分割協議は無効となり、改めて漏れた相続人を加えた上で一からやり直さなければなりません。
「清算型遺贈」で不動産を特定の者に相続。遺言執行者の権限はどこまで?
「清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。
遺言執行者が不動産を売却:清算型遺贈
「清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。
死後離婚(姻族関係終了届)しただけでは「相続放棄」にはならない
「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。
結婚すると、血の繋がりが無い配偶者の血族(両親や兄弟姉妹等)と姻族関係が結ばれます。
遺産分割協議後、認知によって相続人であることが判明した場合
認知によって法律上の親子関係が発生することになりますが、認知は出生のときにさかのぼってその効力を生じるとされています(民法第784条)。
遺産分割協議書に納得できない相続人がいる場合
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に同意したことを証明する書類となります。
亡くなった人から相続人に不動産の登記を移したり、亡くなった人の口座の凍結解除をして預金を払い戻したりする手続きで必要になります。
家庭裁判所の判断による払い戻し制度
既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は別途家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。