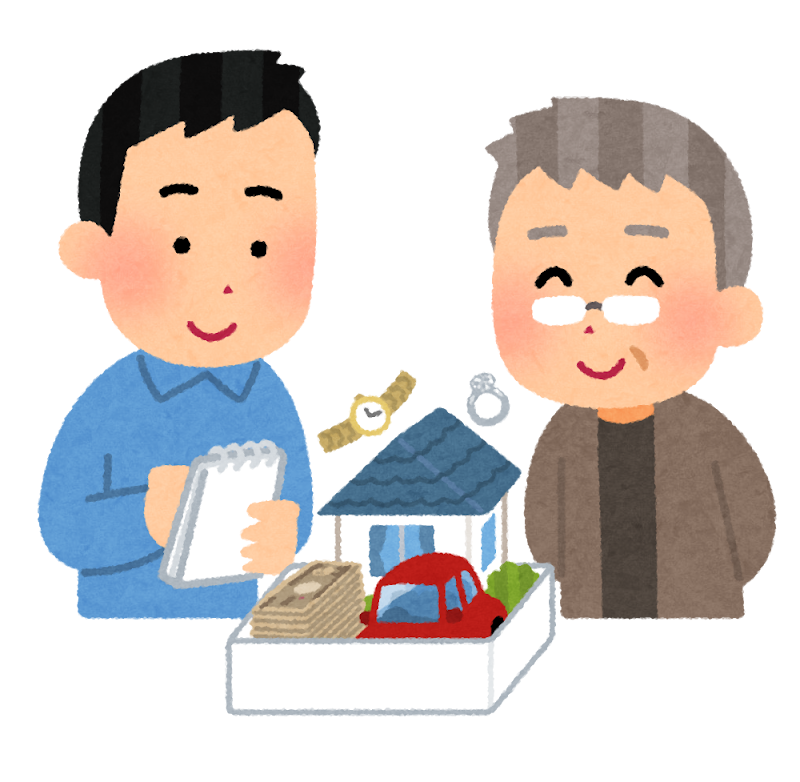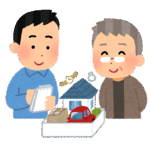賃借人が認知症の場合
1、賃借人が認知症になるリスク
賃借人は、賃貸借契約において、契約で定められた時期に毎月の賃料を支払う義務を負うことになってますが、認知症を発症すると、毎月の賃料を支払うことが困難になり、賃料の支払いが遅滞する事態になる恐れがあります。
また、賃借人は、契約によって定められている用法に従う必要がある(民法第616条、第594条1項)ところ、賃借人が認知症ですと、これに違反してしまう事態も容易に想定されます。
2、解約申立ての相手方は?
賃貸人が、賃貸借契約の更新拒絶、もしくは解約申入れをする場合、賃借人に対して通知することになりますが、認知症を発症していると、意思表示の受領能力なし、として通知の効力が認められません(民法第98条の2)。
なので、更新拒絶や解除を通知する相手方は成年後見人となります。
しかし、家庭裁判所に「成年後見の申し立て」ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等です。
賃貸人(大家)は申立人にはなれません。
そこで、まず賃借人の親族などに「成年後見の申し立て」をお願いするところからスタートとなります。
3、親族などが協力してくれなければ…
賃貸借契約を締結した際の連絡先からなどで親族に連絡。親族が「成年後見の申し立て」に協力的なら、成年後見人が選任された時点で、通知することになります。
これに対し、親族が非協力的、もしくは身寄りがない場合は、市区町村役場に相談。市区町村長に申立てをして頂くよう促すことになります。
[Q7]:市長が後見等開始申立てをすると聞きましたが、親族以外でも申立てができるのでしょうか。
民法上,申立てできる人は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官とされています。
しかしながら,身寄りのないお年寄りなど親族がいない場合もあり,福祉を図るため特に必要があると認められるときは,市町村長にも法定後見開始の申立権が与えられています(老人福祉法32条など)。
(家庭裁判所HP「よくある質問」より)
※参考:「家庭裁判所HP「よくある質問」
※参考:「成年後見制度 市町村長申立てマニュアルQ&A」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市 マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」
マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」