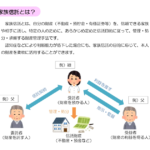[事例]愛人に財産を遺すには
1、事例
㋐相談者(夫:X)。妻(Y)とは長年意思の疎通を図ることができず、事実上家庭は崩壊している。子供が2人(長男、長女)がいる。
㋑最近知り合った女性(愛人:Aさん)と親しくなり、日常生活他、介護、通院の付き添いで世話になっている。
㋒財産は実家、土地、預貯金合わせて5000万円。
㋓相談者としては形だけの家族よりも愛人のAさんに財産を遺してあげたい。
※注意:本事例では不貞による離婚。慰謝料の請求、年金分割などは考慮しないものとする。
2、愛人のために遺言書を作成する
愛人は法定相続人ではないので、「遺贈する」になります。
しかし、妻や2人の子供には「遺留分」(最低限保障される遺産取得分)があります。
金額は法定相続分の1/2。
つまり、妻は1/2×1/2=1/4。2人の子供は各1/4×1/2=1/8です。
相続財産は5000万円なので、妻は1250万円。2人の子供は各625万円となります。
あくまでも「遺留分」は相続人が最低限の財産を受け取ることができる「権利」なので、「愛人に全財産を遺贈する」など、遺留分に反した遺言書も無効ではありませんが、相続発生後、妻や2人の子供が愛人に対し「遺留分侵害額請求権」を行使する可能性が高いと考えられるので、遺言書を作成するなら。遺留分を考慮したものであることが望ましいです。
例えば「愛人に2500万円遺贈する」旨の遺言書なら、妻や2人の子供の遺留分を侵害しているとはいえないので、どうすることもできません。
相続発生時に揉める可能性が高いため、公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
なお、法定相続人以外に遺贈した場合、相続税は2割加算となります。
2、愛人に生前贈与
愛人に生前贈与する方法があります。「年間110万円以内の贈与」なら贈与税はかかりません。
なお、亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前7年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象となります。これを「生前贈与加算」といいます。
「生前贈与加算」は「将来相続人になる人」に対する贈与に適用されます。
愛人は「将来相続人になる人」ではないので、対象外です。
3、愛人に生前贈与と遺留分の関係
「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする(民法第1043条)
具体的には
①故人が相続開始時に有していた財産(不動産、預金、株式、動産等)
②相続人ではない人への1年以内の生前贈与(民法第1044条1項)
③相続人への10年以内の特別受益(民法第1044条3項)
④負債(借金等)
で、①+②+③ー④となります。
愛人は「相続人ではない人」なので、1年以上の生前贈与は遺留分計算の対象外です。
ただし、明らかに遺留分権利者を害する目的で生前贈与を実行すると、裁判で遺留分の対象にされる可能性があるので注意が必要です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。