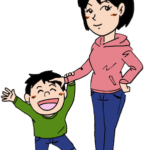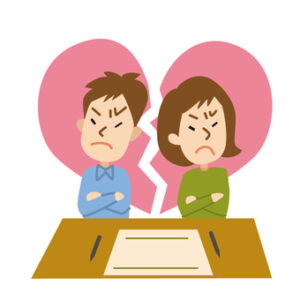夫婦間の扶養義務
1、扶養義務
扶養とは、自らの資産や労力だけでは生活を維持できない者に対する援助のことをいいます。
この「ある者を扶養しなければならない義務」を負う者を扶養義務者といいます。
◎扶養義務の内容
(1)生活保持義務
扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務をいいます。
①被扶養者の配偶者
②未成年の子供の両親
が生活保持義務を負います。
(2)生活扶助義務
扶養義務者自身の生活について、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務をいいます。
兄弟姉妹や、成人の子供に対する両親が負う扶養義務が、この生活扶助義務に該当します。
2、夫婦間の扶養義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)。
夫婦にも扶養義務があると規定しています。
(1)婚姻中の扶養義務
収入が多い方が配偶者を扶養する義務があります
(2)別居中の扶養義務
別居中も、夫婦間には扶養義務があります。
通常「婚姻費用」として毎月一定額を支払うことになりますが、婚姻費用の金額は、裁判所が定めた算定表(養育費・婚姻費用算定表)を基に決めることができます。
未成年の子供がいる場合、婚姻費用には養育費も含まれることから、子供の生活を維持するための費用も計算に含められます。
(3)離婚後の扶養義務
離婚後は、夫婦関係が解消されるため、基本的に扶養義務はなくなりますが、離婚後の生活に不安を抱える配偶者に対し、離婚時の契約により、財産分与として一定期間扶養的な支援を行うことができす。
これを「扶養的財産分与」といいます。
扶養的財産分与は、離婚後に経済的に自立できない配偶者が自立して最低限生活ができるまでの間の生活費を負担するものであり、一般的には、例えば、「離婚日から3年間。毎月○円を支払う」といった具体的な金額と期間を定めます。
3、「扶養」について公正証書に
別居、離婚後の扶養に関する金銭の授受、期間、金額などについては、公正証書による契約が最も安全です。
公証役場の公証人が内容を確認。公正証書にすることにより、内容の適正化が確保されます。
また「強制執行認諾文言」を含めることができ、万が一契約が履行されない場合には、強制執行により迅速に債権の回収を行うことができます。
◎手続き
(1)文案の作成
↓
(2)公証役場での打ち合わせ
↓
(3)公証人による原稿作成
↓
(4)公正証書への調印
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。