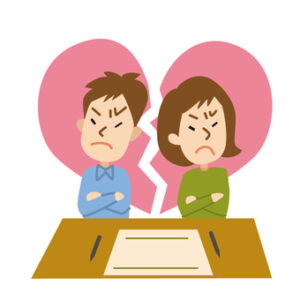事実婚(内縁関係)の配偶者死亡。喪主として葬儀は出来る?
1、死亡届
「死亡届」は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。
=届出義務者=
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。
葬儀社等が代理で届けることもあります。
死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで
①死亡地の市区町村役場
②故人の本籍地の市区町村役場
③届出人の現住所地の市区町村役場
のいずれかに届けます。
事実婚の夫や妻はこの「その他の同居人」に該当します。
なので、死亡届を提出。火葬許可証を発行してもらうことは可能です。
2、葬儀の執り行いに関し「死後事務委任契約」の締結を
確かに事実婚の夫や妻は葬儀を執り行うことができます。
しかし、たとえ日頃から疎遠だったとしても、故人の親族が事実婚に対し良い感情を持っていなかったような場合は多々あると思います。
そこで、生前に遺言書にて、事実婚のパートナーを祭祀主宰者に指定。
同時に葬儀などに関し「死後事務委任契約」を締結しておくことが考えられます。
3、葬儀費用の支払い方法
葬儀費用の支払い方法ですが、一般的には「喪主」が負担することになります。
銀行が被相続人の死亡を知ると口座を凍結しますが、事実婚のパートナーは相続人ではないので、「預貯金の仮払い制度」などを利用して、預金を引き出すことはできません。
あらかじめ、喪主自らが葬儀費用を用意しておく必要があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約
ペット2026年2月4日ペット保険の賠償責任特約 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市