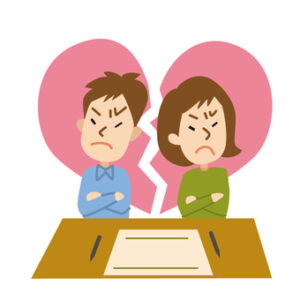「法定の監督義務者に準ずべき者」とは:最高裁平成28年3月1日判決
1、事案
当時91歳で認知症が中等度から重度に進んでいたAは、妻と親族が監視していなかった僅かの隙に家を出て最寄りの駅から乗車。下車したJRの駅構内でホーム先端のフェンス扉を開け線路に降り、進行してきた電車と接触して死亡した。
JRは、Aの妻と成年後見人である長男に対し、民法709条又は714条に基づき、Aの死亡事故による列車遅延等による振替輸送等により生じた損害の賠償請求をした。
2、判決
精神障害者と同居する配偶者だからといって、その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。
法定の監督義務者に該当しない者であっても、
責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、
衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである。
ある者が、精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは、
①その者自身の生活状況や心身の状況などとともに
②精神障害者との親族関係の有無・濃淡
③同居の有無その他の日常的な接触の程度
④精神障害者の財産管理への関与の状況
など。その者と精神障害者との関わりの実情。精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して。
その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。
として、妻と長男は該当しないと判事した。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら
ペット2026年2月4日ペット信託。飼い主が最後までペットを看取ったら 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月3日死後事務委任契約。契約から葬儀に関する事項を外すことができる 終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市
終活、遺品整理、墓じまい2026年2月2日終活支援優良事業者の認証:静岡市 マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」
マンション2026年2月1日近年は「管理会社が管理組合を選ぶ時代」