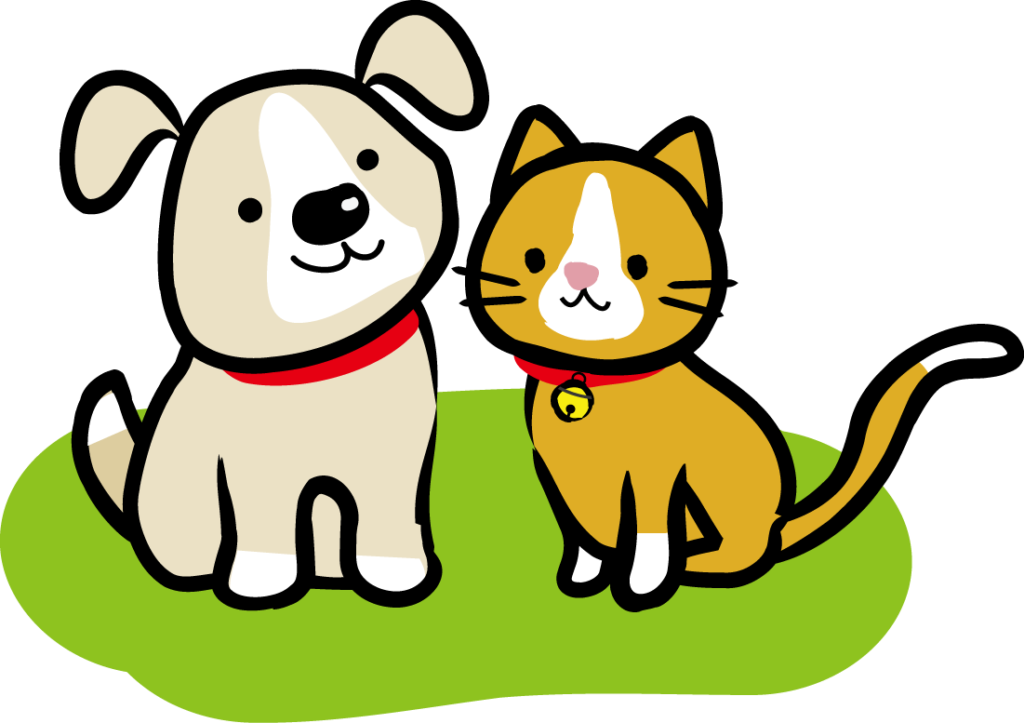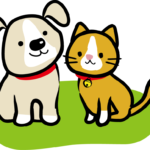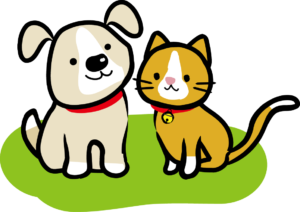愛犬の認知症対策
1、犬の認知症
犬の認知症は、特に高齢犬に見られる病気で、人間と同様、記憶力や学習能力、行動に影響を及ぼし、進行すると徐々に日常生活に支障が出てきます。
具体的には
①徘徊・旋回する、ぼんやりする
②睡眠障害。夜泣きが多くなる
③見当識障害。
飼い主が認識できなくなったり、いつもの場所のフードが見つけられないなどの症状があらわれる。
④排泄ができなくなり、粗相が増える。
などを挙げることができます。
2、犬の認知症予防対策
(1)栄養バランスの取れた食事を与えるシニア犬用のフードには一般的に①ビタミンやオメガ3脂肪酸(EPAやDHA)などの必須脂肪酸製剤②抗酸化物質を含む食材(タウリン、ポリフェノールなど)が多く含まれています。こうしたフードを選び、必要に応じサプリメントなどの補助食品も一緒に与えてあげるのが有効です。
(2)夜泣きや徘徊への対策日中に活動させて夜に寝る習慣をつけるため、朝はカーテンを開ける、夜は静かに過ごすなどを意識することにより、体内時計を安定させ、夜間の不穏な行動を減らす効果が期待できます。
(3)脳を刺激する日常的に知育玩具や「おすわり、まて、くるん」などの練習を続けることで、脳への良い刺激になります。
(4)定期的に運動する運動は血流改善、ストレス緩和、筋力維持など多くのメリットがあります。また、外界からの刺激(匂い、音、光)が認知機能を保つ秘訣となります。
3、老犬ホームに預ける
動物愛護法により、飼い主が飼い犬の飼育をすることが義務付けられています。
しかし、飼い犬が高齢になり、認知症を発症すると、粗相し続ける、昼夜問わず泣き続けるなど、飼い主が世話できなくなることもあります。
飼い犬への愛情故に手放すのは心苦しい部分もあるかと思いますが、飼い犬の本当の幸せを考えるなら、老犬ホームで飼い犬の世話を依頼するのも一つの方法です。
一般的に老犬ホームに入所するには
①入所金:老犬ホームに愛犬を預ける際に支払う費用
②基本料金:施設で預かる際に必要な費用
③介護料金:毎日の介護にかかる費用
④預り金:愛犬が入所している間に医療費にあてるための費用
などが必要です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)
国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き) 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する
国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要
国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要