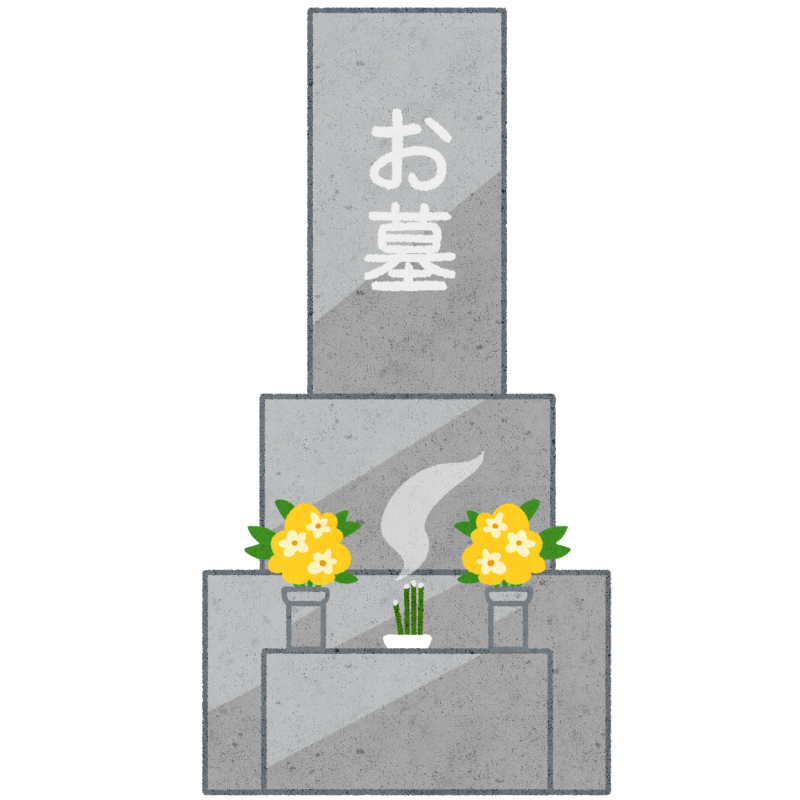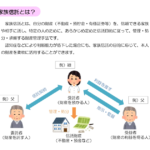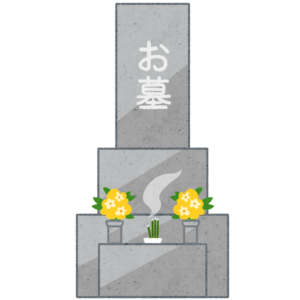墓地使用権型標準契約約款
1、墓地使用権型標準契約約款:目的
(目的)
第1条 本約款は、財団法人○○[宗教法人△△]が経営する墓地(以下「墓地という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定め、その使用及び管理が適切に行われることを目的とする。
①本契約約款が何を対象とし、何のために定められているのかを明確にしておくことが大切
②墓地使用契約は双務契約であり、使用者に一方的に義務を課すような規定は好ましくない
2、墓地使用権型標準契約約款:墓地の使用
(墓地の使用)
第2条 使用者は、次に掲げる墓地の区画(以下「墓所」という。)を、契約成立後○年間[第8条又は第9条の規定により契約が解除されない限り、継続して]使用する権利を有する
使用場所
2 使用者は、経営者に届け出て、墓所内に使用者の親族及び縁故者の焼骨を埋蔵することができる。
3 使用者は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓所を使用してはならない。
4 使用者は、経営者の承諾を得ずに墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させてはならない。
①本条は、使用者の墓地使用権及び使用に当たっての条件等について規定したものである。
②墓地の使用期間については「永代」とされている場合が多いものの、管理料の不払い等が発生すれば契約解除となることが想定されるため、「契約が解除されない限り継続して」の表現の方が望ましい。
③この方式を規定した場合、第6条の更新手続は不要であり、使用者としての義務を履行していれば特段の手続なく使用し続けることが可能である。
④ただし、使用者が死亡した場合の使用継続の届出(第7条)は必要である。
3、墓地使用権型標準契約約款:使用料
(使用料)
第3条 使用者は、経営者が定める期日までに使用料○円を支払わなければならない。
①墓地使用権設定の対価である「使用料」と墓地の維持管理に充てるための「管理料」を個別に想定することにより、何に対する料金であることを明確にした。
②使用料の不払いは、経営者による解除の要件となります(第9条第1項)。
4、墓地使用権型標準契約約款:墓地の管理
第4条 墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負う。
2 墓地の環境整備その他の管理(前項に規定するものを除く。)については、経営者がその責任を負う。
①本条は、墓地の管理について誰が責任を負うかを明らかにするものである。
②第2項では、墓地全体の管理については、使用者が責任を負う墓所の清掃等を除き、経営者が責任を負うことを規定したものである。これは管理料の請求の根拠にもなるものである。
③なお、本契約約款では経営者が免責される場合は規定していないが、地震、火災等の不可抗力の場合について使用者との関係で経営者が免責される場合を定めておくことも考えられる。
5、墓地使用権型標準契約約款:管理料
(管理料)
第5条 経営者は、前条第2項に要する費用に充てるため、別に定めるところにより、使用者に対して毎年管理料を請求するものとし、使用者はこれを支払わなければならない。
2 経営者は、物価の変動等により、当該時点における管理料によっては前項に規定する費用を賄うことができなくなったとき、又はその確実な見込みが生じたときは、必要かつ相当と認められる範囲内において、管理料を改定することができる。この場合において、経営者は、改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対し、事前に書面により通知するものとする。
①管理料の使途については、これを明確にしないまま使用者に支払義務を課すことは妥当でなく、何のために管理料をとるのかをはっきりさせておく必要がある
②物価変動等により墓地の管理に要する費用が賄えなくなった場合(又は確実に見込まれる場合)に限り、必要かつ相当と認められる範囲内でのみ改定が可能などという制限を設けることが望ましい。
③さらに、改定ついて理由も含めて、書面により利用者にあらかじめ通知することにより、一層の使用者保護が図られるものである。
6、墓地使用権型標準契約約款:契約の更新
第6条 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後も継続して墓所を使用しようとする者は、当該期間が経過する○年前から、経営者に対して契約更新の申込みをすることができる。
2 前項の申込みがあった場合において、前条第1項に規定する管理料の支払義務が履行されている場合には、経営者は前項の申込みを承諾しなければならない。
①第1項においては、使用期間終了の前から更新の申込手続ができることを規定している。
②第2項においては、管理料の支払が行われていることを条件として、経営者が更新の申込みを必ず承諾しなければならないことを規定したものである。
7、墓地使用権型標準契約約款:使用者の地位の承継
第7条 使用者の死亡により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓所の使用を継続する場合には、当該祭祀承継者は、すみやかに別記様式による地位承継届出書に住民票の写しを添えて経営者に届出を行うものとする。
2 使用者の祭祀承継者が墓所の使用を継続しない場合には、書面をもって経営者にその旨を届け出るものとする。
①第1項は祭祀承継者が使用を継続する場合の規定である。
民法第897条第1項により、墓地使用権については当然に祭祀承継者に承継されるものであるから、本契約約款では特に承継に際しての経営者の承認等の関与は定めていない。
経営者としては、誰が承継して墓所を使用するのかを把握しておくことが重要なので、承継者が住民票の写しを添えて必要な事項を書面をもって届け出るべきことを明確に義務付けた。
②第2項は祭祀承継者が使用を継続しない場合の規定である。
この場合、契約が終了することとなるため、書面による意思表示を求めることとしている。
8、墓地使用権型標準契約約款:使用者による契約の解除
第8条 使用者は、書面をもっていつでも契約を解除することができる。
2 前項の場合においては、使用者は既に支払った使用料及び管理料の返還を請求することはできない。ただし、墓所に墓石の設置等を行っておらず、かつ焼骨を埋蔵していない場合において、使用者が既に使用料 納付しているときは、契約成立後○日以内に契約を解除する場合に限り、経営者は、当該使用料の○割に相当する額を返還するものとする。
3 第1項の場合において、契約解除の日の属する年[度]の管理料を納付していないときは、使用者は当該管理料を支払わなければならない。
①本条は使用者側からの墓地使用契約の解除権及び解除権が行使された場合の料金の取扱いについて規定したものである。
②契約の終了につながる重要事項であるため後でトラブルが起こることのないよう、書面による意思表示を求めることが適当である。
9、墓地使用権型標準契約約款:経営者による契約の解除
第9条 経営者は、使用者が使用料を所定の期日までに支払わなかったときは、書面をもって、契約を解除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、使用者が次の各号の一に該当する場合には、経営者は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、書面をもって、契約を解除することができる。
一 ○年間管理料を支払わなかった場合
二 第2条第3項に規定する使用の目的に違反して墓所を使用した場合
三 第2条第4項の規定に違反して墓所を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓所を使用させた場合
①本条は、経営者側からの解除権の行使について、催告を要する場合と要しない場合に分けて規定したものである。
②使用料の支払は、墓地使用権設定の対価であり、かつ墓地使用契約の中で使用者が負う債務の中心的要素である。
したがって、これを履行しないことは重大な契約違反であることから、特に催告については規定せず、書面をもって解除することができることとしている。
③一定期間の管理料の不払い及び使用者が墓地使用に関する制約を遵守しなかったことは、使用料の不払いと比べて、墓地使用に対する直接かつ重大な債務不履行とまでは必ずしもいえないことから、いったん催告して履行を促すこととしたものである。
10、墓地使用権型標準契約約款:契約の終了及びこれに伴う措置
第10条 契約は、次に掲げる場合に終了する。
一 墓所を使用する権利を有する期間が経過した後、第6条第1項に規定する契約更新の申込みがなされなかったとき
二 第7条第2項の届出があったとき
三 前二条の規定により契約が解除されたとき
2 契約が終了したときは、使用者であった者又はその祭祀承継者(次項及び第項において「元使用者等」という。)は、速やかに墓所内に設置された墓石等を撤去し、墓所内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。
3 元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後○年経過した場合には、経営者は、墓石等を墓地内の所定の場所に移動し、及び法令の規定による改葬手続を経て埋蔵された焼骨を墓地内の合葬墓又は納骨堂に移すことができる。
4 前項の場合においては、経営者は実費を元使用者等に請求することができる
①本条は、墓地使用契約がどのような場合に終了するかということ及び契約が終了したときにどのような措置がなされるかについて規定したものである。
※参考:「厚生労働省HP「墓地経営・管理の指針等について」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
 国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する
国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する 国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要
国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要 国際結婚、国際離婚2026年2月21日タイ人との国際結婚手続き(先にタイで手続き)
国際結婚、国際離婚2026年2月21日タイ人との国際結婚手続き(先にタイで手続き) 国際結婚、国際離婚2026年2月21日タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
国際結婚、国際離婚2026年2月21日タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)